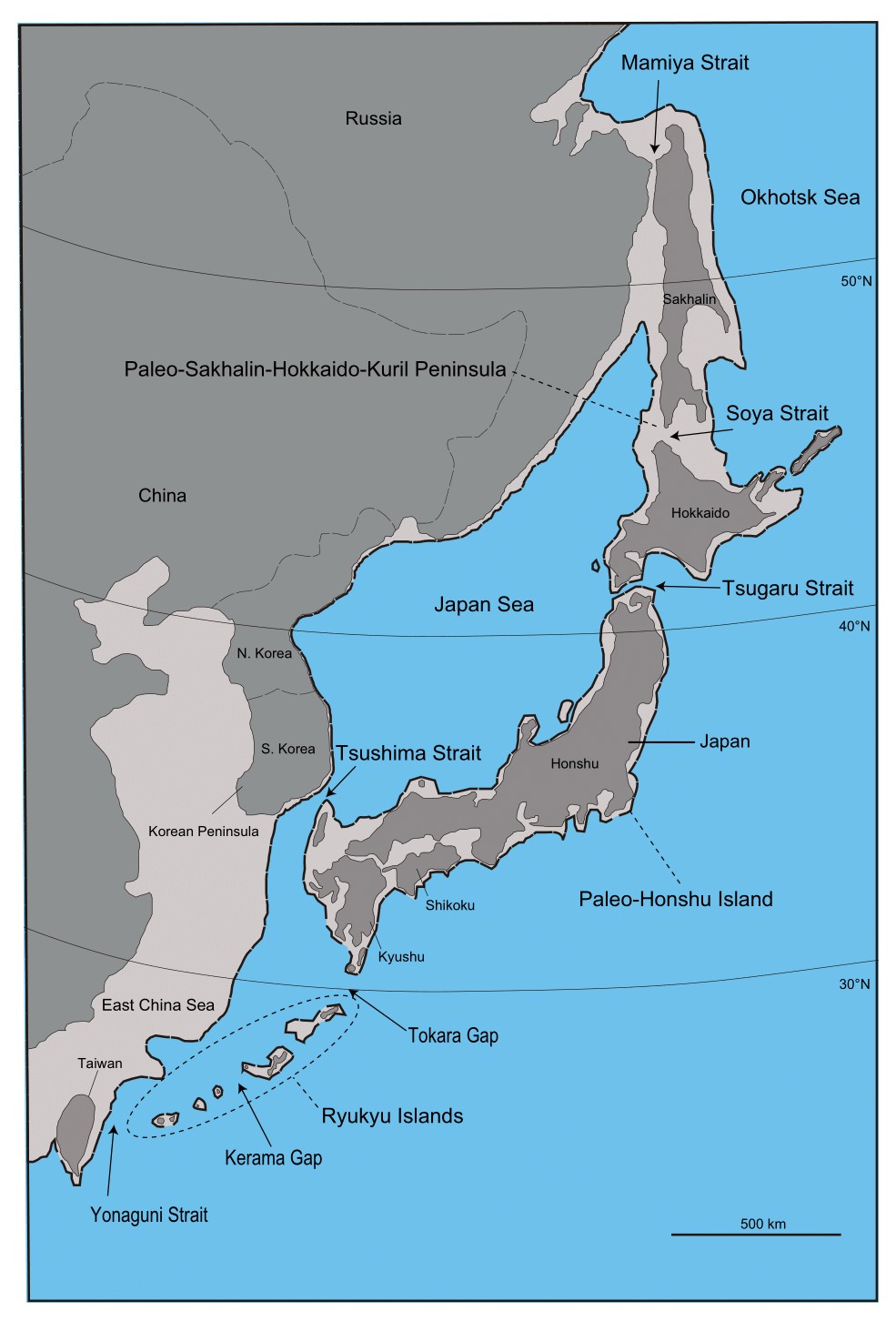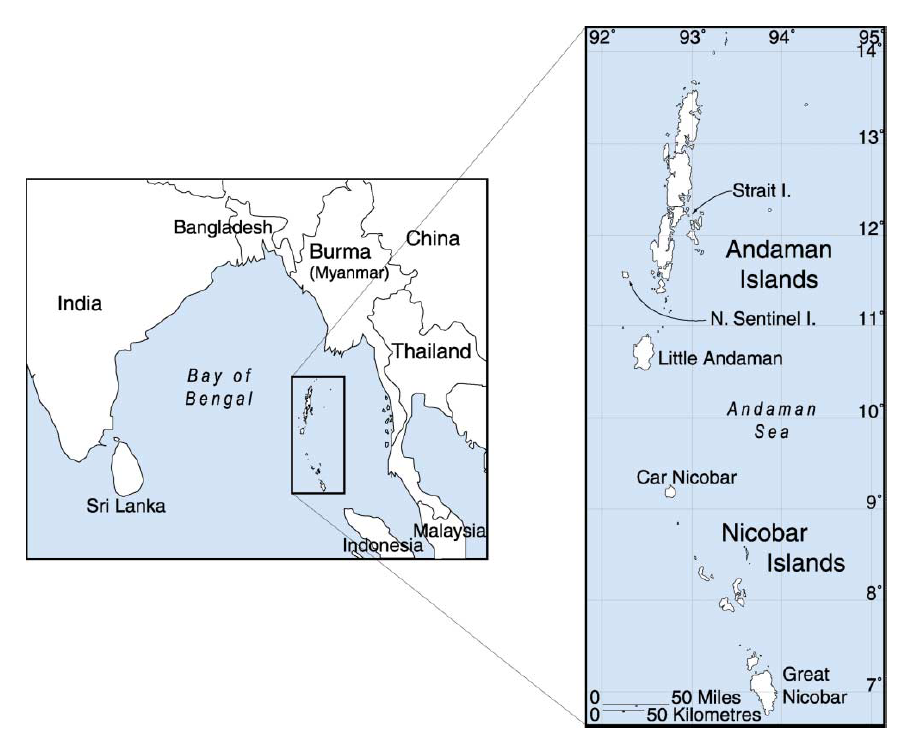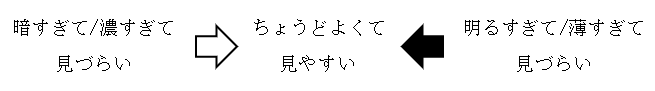「はきはきと答える」のhakihakiと「はっきりと答える」のhakkiriは、使われ方にいくらか違いはありますが、十分な共通性が感じられます。タイ語のpaak(口)のような語が日本語のpakupaku、pakkuriになったのと同様に、古代中国語のbæk(白)バクが日本語のhakihaki、hakkiriになったのではないかと考えさせます。すでに説明したように、日本語にはsiro(白)という語があるので、古代中国語のbæk(白)は単純に「白」を意味することができず、「光、明るさ、明瞭さ、明確さ、明白さ」などのほうに向かいやすい状況にありました。
※ちなみに、タイ語には「はっきりした、明瞭な、澄んだ」などの意味を持つsayサイという基本語があります。このような語から、奈良時代の日本語のsayaka(さやか)やsayu(冴ゆ)が作られたようです。現代では、sayaka(さやか)はほぼ廃れていますが、sayu(冴ゆ)はsaeru(冴える)になって残っています。「頭が冴えない」と言う時のsaeru(冴える)です。
日本語にはhakihaki(はきはき)、hakkiri(はっきり)のほかに、paʔ(パッ)という擬態語もあります。日本語の発音体系では、古代中国語のbæk(白)のkをこのまま放置することはできず、このkのうしろになにか補うか、このkを取り除くかしなければなりません。古代中国語のbæk(白)がkのうしろになにか補われて日本語に入り込んだ可能性もあれば、古代中国語のbæk(白)がkを取り除かれて日本語に入り込んだ可能性もあるのです。
現代の日本語でも、光や明かりに関して「パッと光る」とか「パッとつく」のように言うことができます。筆者は、「光、明るさ、明瞭さ、明確さ、明白さ」などの意味領域に傾きつつあった古代中国語のbæk(白)がhakihaki(はきはき)、hakkiri(はっきり)という形だけでなく、paʔ(パッ)という形でも日本語に入り込んだと見ています。光や明かりによって、視界が一変することにも注意してください。光・明るさを意味していたpaʔ(パッ)は、目になにかが飛び込んでくること、目の前になにかが現れること、目の前になにかが広がること、場面の変化・切り替え、展開、進展、素早い動作・・・という具合にどんどん意味領域を広げていったと見られます。「お酒をパーッと飲む」や「お金をパーッと使う」のpāʔ(パーッ)は、明るさから陽気さや派手さのような意味が生じており、これも同類と考えてよいでしょう。
paʔ(パッ)は上記のように素早い動作も表すようになりましたが、papaʔ(パパッ)という言い方もあります。このpaʔ(パッ)、papaʔ(パパッ)のおおもとが古代中国語のbæk(白)だとしたら、同じように素早い動作を表すsaʔ(さっ)、sasaʔ(ささっ)はどうでしょうか。これもやはり、sauという読みで日本語に取り入れられた古代中国語のtsaw(早)ツァウが怪しいのです。古代中国語のbæk(白)がpaʔ(パッ)、papaʔ(パパッ)に、古代中国語のtsaw(早)がsaʔ(さっ)、sasaʔ(ささっ)になったのではないかということです。
古代中国語のbæk(白)が、meihaku(明白)、keppaku(潔白)、zihaku(自白)のような硬い書き言葉だけでなく、hakihaki(はきはき)、hakkiri(はっきり)、paʔ(パッ)、papaʔ(パパッ)のようなごく普通の話し言葉としても日本語に入り込んでいるらしいというのは、なんとも驚きです(歴史を振り返れば、言語の研究は明らかに書き言葉を中心に行われてきたので、古代中国語と日本語の擬態語の関連性を指摘する声がほとんどなかったのも致し方のないことかもしれません)。bæk(白)は一例として挙げているだけであって、これは日本語の擬態語全体、さらには中国語と日本語の関係全体に関わる話です。古代中国語のbæk(白)から日本語のhakihaki(はきはき)、hakkiri(はっきり)、paʔ(パッ)、papaʔ(パパッ)などが作られて、これらを「擬態語」という名の下で特別扱いすることが妥当なのかという問題もあります。
上に示した古代中国語のbæk(白)と日本語の擬態語のような例は膨大にあるので、徐々に紹介していきますが、ここではとりあえず、イメージを膨らませるために三つほど例を追加します。
●古代中国語のpjuwng(風)
日本語のkaze(風)(古形*kaza)に関係がありそうな語はウラル語族に見られ、特にサモエード系のほうに、ネネツ語xad(吹雪)ハドゥ、エネツ語kazu(吹雪)、ガナサン語koðu(吹雪)コズ、マトル語kadu(嵐)のような語があります。日本語のkaze(風)には、かなり古い歴史がありそうです。その一方で、古代中国語では風のことをなんと言っていたのでしょうか。古代中国語ではpjuwng(風)ピウウンと言っていました。おやっと思ってしまうのは、おそらく筆者だけではないでしょう。日本語のpyūpyū(ぴゅうぴゅう)、hyūhyū(ひゅうひゅう)、byūbyū(びゅうびゅう)とは一体なんなのかと考えざるをえません。
●古代中国語のtsjowk(足)
古代中国語のtsjowk(足)ツィオウクは、昔の日本語の話者にとって相当な難物だったはずです。古代中国語のtsjowk(足)はある時代にsokuという読みで日本語に取り入れられましたが、tsjowk(足)→soku以外の変形もありえます。tsjowk(足)の先頭の不慣れな子音ts(ツァ、ツィ、ツ、ツェ、ツォの類)をs(サ、スィ、ス、セ、ソの類)に変換するのも一つの手ですが、t(タ、ティ、トゥ、テ、トの類)に変換するのも一つの手です。tsjowk(足)→sokuだけでなく、例えばtsjowk(足)→tokVやtsjowk(足)→tukVという変形も可能です(Vは補われる母音です)。現代の日本語のようにtya、tyu、tyoの類やouのような母音連続が当たり前の時代だったら、tsjowk(足)をtyoukV、tyokV、tyukVと変形することも可能ですが、そうでなかった時代には、tsjowk(足)をtokV、tukVと変形するのが自然なのです。こうして作られたのが、日本語のtokotoko(とことこ)やtukatuka(つかつか)と見られます。言ってみれば、tokotoko(とことこ)やtukatuka(つかつか)は「足足」のような表現なのです。
●古代中国語のdrim(沉)
古代中国語のdrim(沉)ディム(日本語では「沈」という字を用いています)は、日本語ではtinという音読みが一般的になりましたが、din、zin、sinと読まれることもありました。ここで、日本語においてsizumu(沈む)がsizumaru(静まる)やsizuka(静か)と同源であることを考えると、なんの音もしないことを表すsīn(シーン)の存在が気になります。なんでなんの音もしないのにsīn(シーン)なのかと思いあぐねた方もいるかもしれません。「雪がしんしんと降る」のsinsin(しんしん)も同類です。このsīn(シーン)、sinsin(しんしん)も、擬態語でない普通の語がもとになっていると考えられます。その普通の語とは、日本語でdin、tin、zin、sinと読まれた古代中国語のdrim(沉)ではないかと考えられるのです。
「日本語の意外な歴史」では、擬態語と呼ばれてきた語を特別視するようなことはせず、普通の名詞、動詞、形容詞などといっしょに扱っていきます。擬態語の語源も、普通の名詞、動詞、形容詞などの語源と変わりないからです。
日本語のいわゆる擬態語は、大きな見直しが必要です。