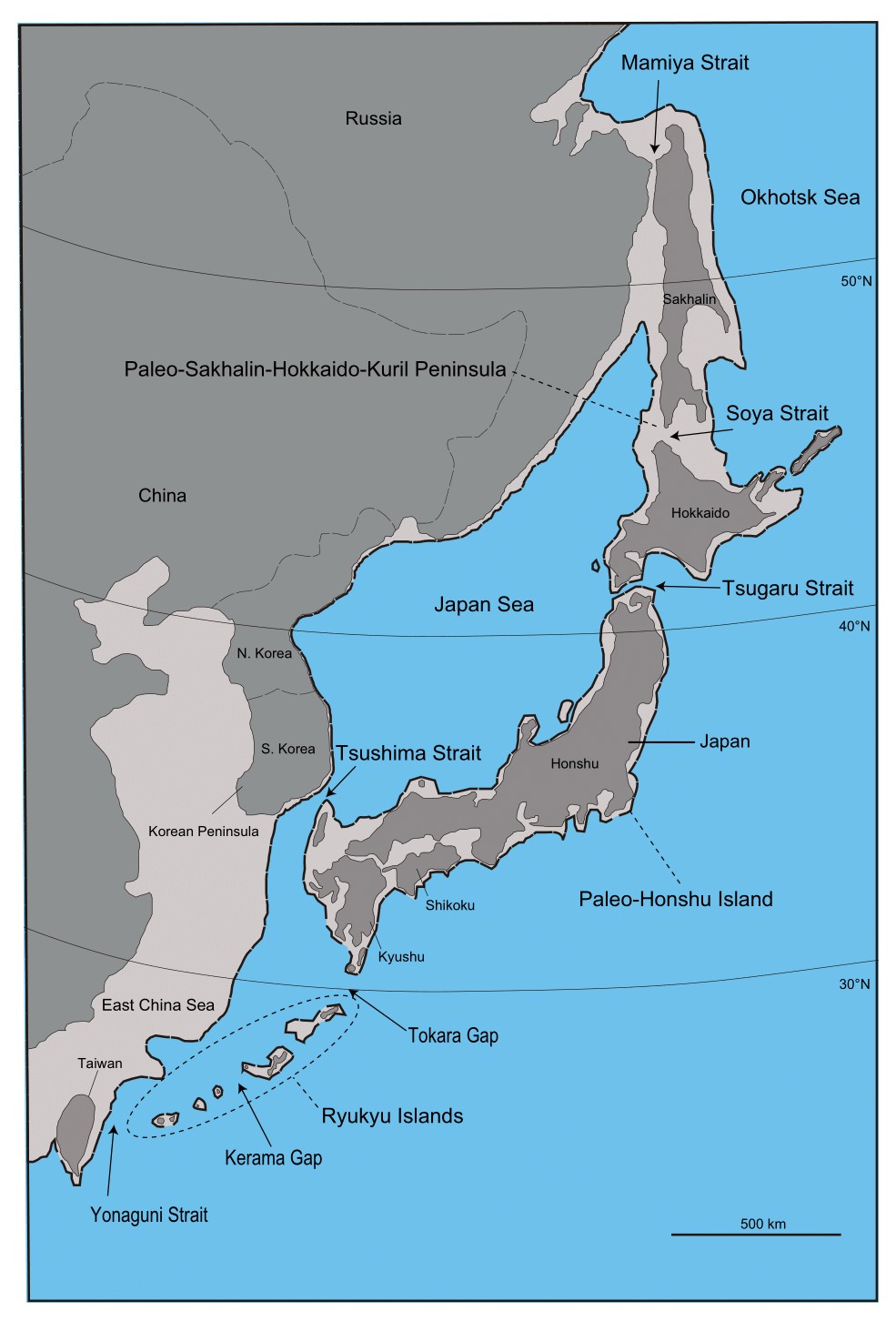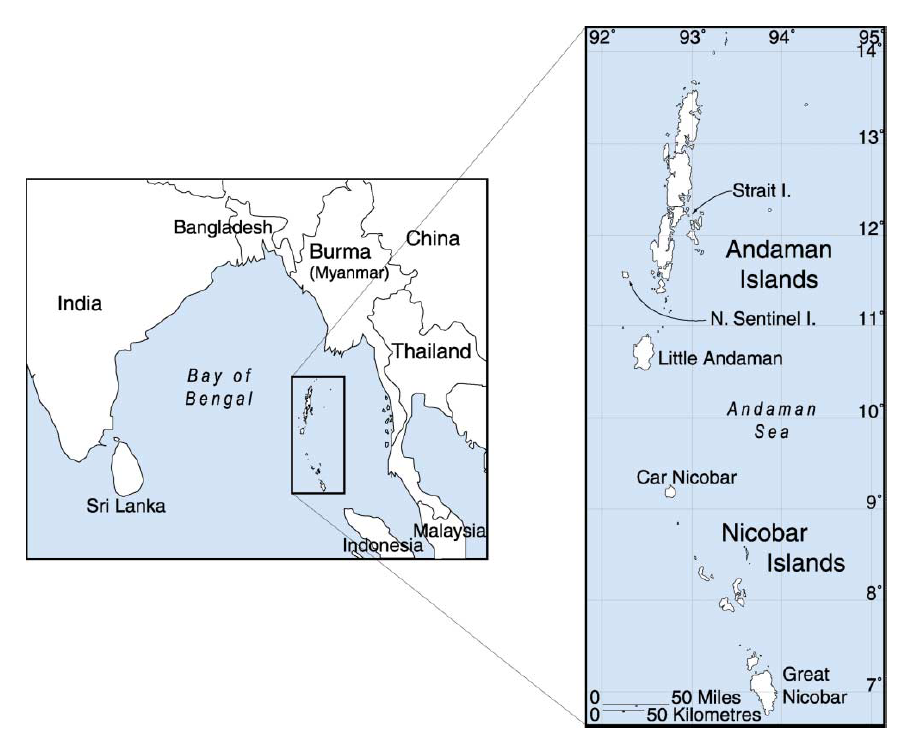古代中国語からseisin(精神)という言葉が取り入れられ、kokoro(心)と同じようによく使われています。日本人の普通の感覚では、「精神」は完全に一語であり、その内部構造を考えることはまずないと思いますが、なぜここに「神」が出てくるのかということは考える必要があります。人類の言語の歴史を遠く遡る際には、現代とは違う時代を生きた古代人の感覚や考えを理解することが必須になってきます。
現代の日本語にkarada(体)、nikutai(肉体)という語がありますが、これらと対になるような語を思い浮かべてください。どのような語が思い浮かぶでしょうか。kokoro(心)、seisin(精神)、tamasii(魂)、reikon(霊魂)、rei(霊)などの語が思い浮かぶでしょう。これらの語は、karada(体)/nikutai(肉体)と対になるという点で、ゆるやかではありますが、意味的なまとまりを感じさせます。
このkokoro(心)、seisin(精神)、tamasii(魂)、reikon(霊魂)、rei(霊)という一群の横に、kami(神)を並べるとどうでしょうか。現代人なら、kami(神)は異質だと思うのではないでしょうか。しかし、古代人には古代人の見方がありました。古代人は、人の体があって、そこになにか(霊)が宿っている、山があって、そこになにか(霊)が宿っている、海があって、そこになにか(霊)が宿っている、そういう見方をしていたのです。この人の体およびその他のすべてのものになにか(霊)が宿っているとする信仰は、精霊信仰あるいはアニミズムと呼ばれ、人類の歴史に普遍的に認められます。
古代中国語のleng(靈)レンも、tsjeng(精)ツィエンも、hwon(魂)フオンも、zyin(神)ジンも、そのように宿るなにかを意味する類義語だったのです。精+靈→精靈、精+魂→精魂、精+神→精神のように似た語をくっつけて新しい語を作るのは、中国語のお得意のパターンです。
上にkokoro(心)、seisin(精神)、tamasii(魂)、reikon(霊魂)、rei(霊)、kami(神)という語を並べましたが、このような意味領域に属する語は、当然ベトナム語にもいくつかあります。実は、ここに興味深い語があるのです。tâmタム、tríチー、そして tâm trí タムチーです。tâmは心を意味し、tríは精神、思考を行う部分、知性、知能などを意味します。両者が組み合わさったのが tâm trí です。
なぜベトナム語のtâmタム、tríチー、 tâm trí タムチーが興味深いかというと、奈良時代の日本語のtama、ti、tamasiɸiによく一致するからです。奈良時代の日本語のtamaとtiについて、三省堂時代別国語大辞典上代編(上代語辞典編修委員会1967)は以下のように述べています。先ほど言及した精霊信仰・アニミズムのことを頭に入れながら読んでください。
「古代日本人を支配した超自然的霊格におおよそチ・タマ・カミの三種があり、チの観念が最も古く発生し、タマはこれに次ぎ、カミが最も新しいという。万葉では、その中、チはほとんど痕跡を止めず、タマもその観念をカミに吸収され、ひとりカミと呼ばれる霊格が、宗教的崇拝ならびに祭儀実修の対象のほとんどであった。」
「霊」と書き表されたtiは現代の日本人に全然なじみがありませんが、tamaはhitodama(人魂)などの形で残っています。現代の日本語のtamasiiは「魂」と書かれますが、奈良時代の日本語のtamasiɸiは「魂」と書かれるだけでなく、「心」と書かれたり、「精神」と書かれたり、「識性」と書かれたりもしました。
上に挙げたベトナム語のtâm、trí、 tâm trí と日本語のtama、ti、tamasiɸiを比べると、発音がよく一致していますが、tamasiɸiに含まれているɸが気になるところです。このɸは挿入されたものと考えられます。tamasiiと母音が連続するのを嫌って、ɸを挿入したということです(pを挿入して、それがɸに変化した可能性もあります)。
例えば、奈良時代の日本語のtiɸisasi(小さし)も同様です。「細かいこと」を意味した古代中国語の tsi sej (子細、仔細)ツィーセイまたはこれに近い形を取り込む時に、tiisa-とせずにtiɸisa-としたと見られます(pを挿入して、それがɸに変化した可能性もあります)。
このようなことを考慮に入れると、ベトナム語のtâm、trí、 tâm trí と日本語のtama、ti、tamasiɸiはやはりよく一致します。ベトナム語のtríのような語を取り込む時に、日本語に全く同じ子音がなく、tを用いたり、sを用いたりしていたと思われます。
ちなみに、ベトナム語のtríチーは古代中国語のtrje(智)ティエおよびtrje(知)ティエと関係があるとされている語です。これらと日本語のsiru(知る)は関係があるのかということも問題になりますが、筆者はその可能性は微妙だと考えています。古代中国語にはtrje(知)の類義語としてsik(識)という語があり、この語はsiki、syoku、siという音読みで日本語に取り入れられました。日本語のsiru(知る)は古代中国語のsik(識)から来ている可能性のほうが高いように思います。古代中国語のak(惡)をaにし、これにsiを付けてasi(悪し)という形容詞を作ったのと同じように、古代中国語のsik(識)をsiにし、これにruを付けてsiru(知る)という動詞を作ったのではないかということです。
古代中国語とベトナム系言語と日本語の間はなかなか複雑で、「古代中国語→ベトナム系言語→日本語」という語の流れも考える必要がありそうです。
それでは、棚上げしていたtanosi(楽し)の語源の考察に入りましょう。
補説
tama(魂)とtama(玉)
「霊」という漢字は、昔の中国では「靈」と書かれていました。「靈」の異体字として、以下の漢字も見つかっています。

どうやら、古代人の世界では、霊と玉の間になんらかの結びつきがあったようです。霊が玉に依りつくようにしていたのかもしれません。三省堂時代別国語大辞典上代編(上代語辞典編修委員会1967)では、奈良時代の日本語のtama(魂)とtama(玉)は同源であろうと推測していますが、正しそうです。東アジアの一部に限られた話かもしれません。
参考文献
上代語辞典編修委員会、「時代別国語大辞典 上代編」、三省堂、1967年。