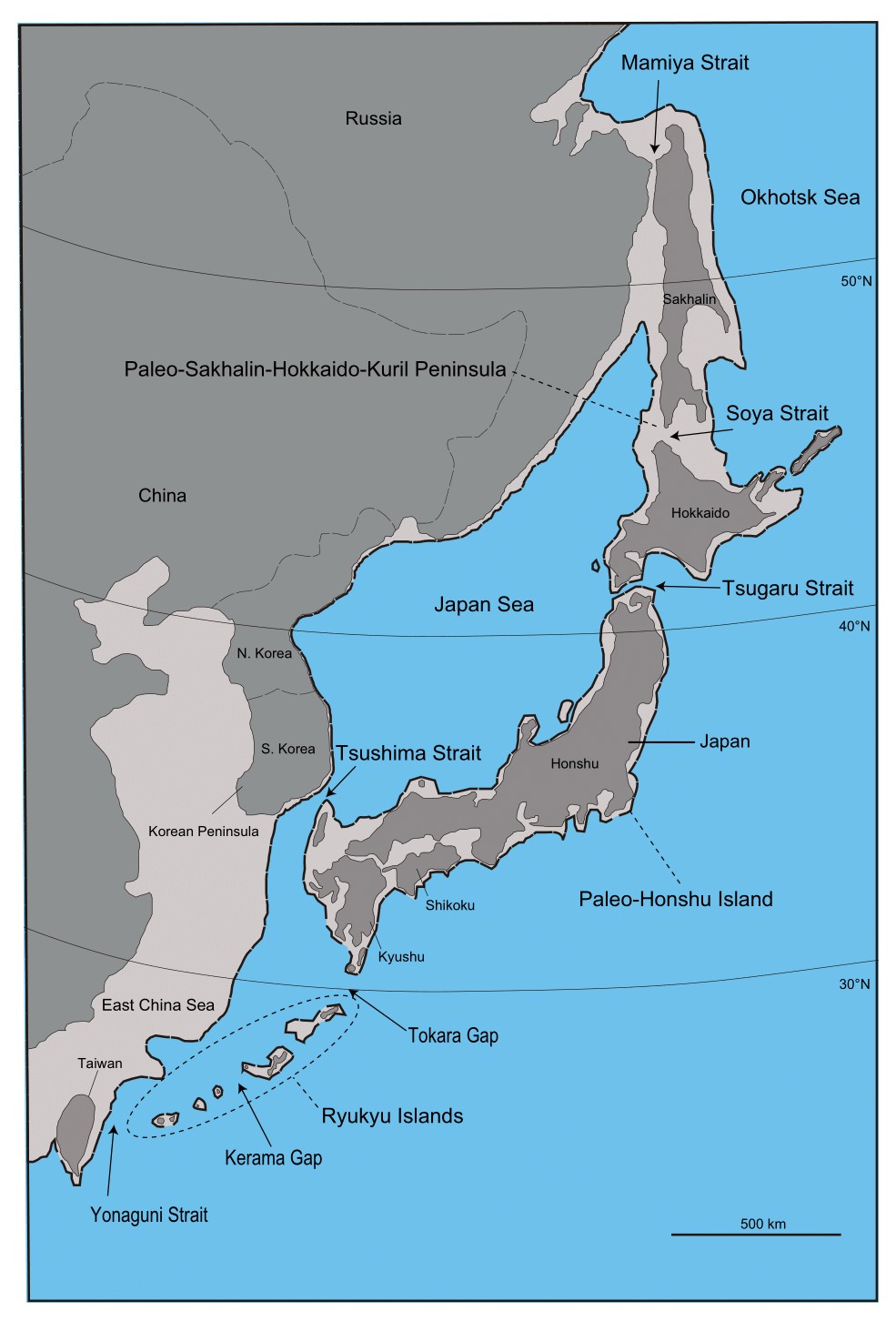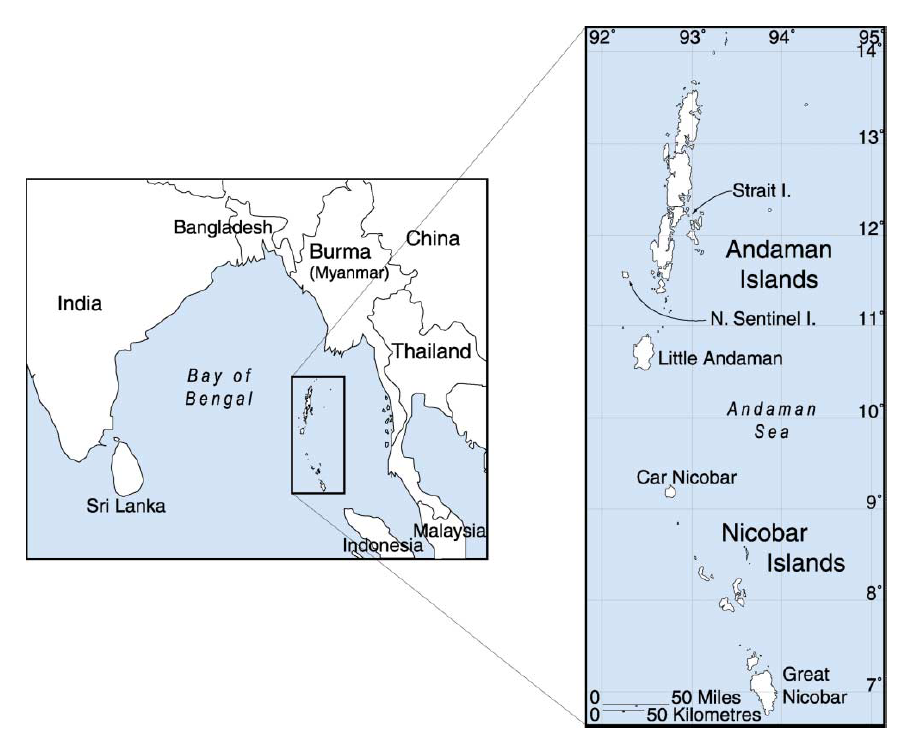ウラル語族では、*najVのような語が「女」を意味していたようだとお話ししました。「女」を意味する語も重要ですが、「母」を意味する語も重要です。
現代のフィンランド語ではäitiアイティが「母」を意味していますが、この語はインド・ヨーロッパ語族からの外来語です。もともと「母」を意味していたのは、emäエマです。emäは今でも残っていますが、「動物の母親」を意味するだけになっています。フィンランド語のemäと同源の語も、ウラル語族全体に分布しています。
フィンランド語のemä(動物の母親)に対応するのは、エストニア語ではema(母)、ハンガリー語ではember(人)のemの部分、ネネツ語ではnjebja(母)ニェビャです。ウラル語族には、女と男の対を表す語が「人」を意味するようになるケースがあり、ハンガリー語のemberもそのようなケースではないかと考えられています( Zaicz 2006 )。ネネツ語は語頭に母音が来るのを避けるためになんらかの子音を前に補う傾向があるので、njebjaとなっています。
ウラル語族では、*najVのような語が「女」を意味し、*emVのような語が主に「母」を意味していたようです。しかしながら、「母」と「女」の間は単純ではありません。
祖父、父、おじに対してはフィンランド語のisäイサのように言い、祖母、母、おばに対しては厳密に別々の言い方をしていたというのは、ちょっと考えづらいことです。*emVの使用範囲が母より広かった可能性は十分にあります。祖母、母、おばに対して*emVと言い、必要に応じて*emVに語句を補うというやり方も考えられます。あるいは、ある子どもを連れている女性を*emVと呼び、別の子どもを連れている女性を*emVと呼び、さらに別の子どもを連れている女性を*emVと呼んでいるうちに、*emVが女性一般を意味するようになっていくかもしれません。
前にウラル語族の各言語で「女」のことをなんと言っているか表に示しましたが、フィンランド語nainen(女)、ハンガリー語nő(女)ノー、ネネツ語nje(女)ニェのような語が大部分を占めていました。しかし、ハンティ語imi(女)、セリクプ語ima(女)という語もありました。ハンティ語には、imi(女)のほかに、omi(母)やime(妻)のような語があります。セリクプ語には、ima(女)のほかに、ama(母)やimatɨ(妻)イマティのような語があります。ハンティ語とセリクプ語の例は、遠い昔に存在したある語を単純に受け継ぐだけでなく、母音を交替させたり、要素を追加したりしながら、語彙を増やしているように見えます。フィンランド語のemä(動物の母親)などと無関係でないであろうハンティ語のomi(母)、imi(女)、ime(妻)やセリクプ語のama(母)、ima(女)、imatɨ(妻)は、奈良時代の日本語に存在したomo(母)とimo(妹)を強く思い起こさせます(日本語の場合は、エ列の音がない時代があったと考えられるので、ウラル語族の*emVに対応する語があったとしても、語頭の母音はeにはなりません)。
日本語のomo(母)は、奈良時代にɸaɸa(母)とならんで使われていた語です。振り返れば、奈良時代はomo(母)からɸaɸa(母)への移行期だったのでしょう。omo(母)は廃れ、同類と見られるomo(主)が残ることになりました。
それに対して、万葉集などに頻繁に出てくるimo(妹)は、現代の私たちにはやや理解しづらい語です。三省堂時代別国語大辞典上代編(上代語辞典編修委員会1967)では、基本的に「男から妻や恋人・姉妹などの親しい女性を呼ぶ称」とし、「イモは男から恋愛の対象となる女性一般をよぶ称であったらしい」という見解を述べています。古代の日本では(母親が異なる)兄弟姉妹間で子が作られることもあり、この点も現代と事情が違います。
生まれてきて出会う女性の中で、まず大きな存在となるのは、母でしょう。しかし、人生には、母以外の特別な女性もいるでしょう。女性一般を指す語としては*nayo(女)→me(女)があったので、imo(妹)はいくらかの変化の過程を経て三省堂時代別国語大辞典上代編が説明するような位置づけになったと見られます。世代や男女関係などを考えても、「祖母、母、おばの類」と「妻、恋人、姉妹の類」のような区別は不自然ではないでしょう。
*isa、*nayo、omo(母)、imo(妹)と見てきました。奈良時代の日本語には、ウラル語族の男と女に関する代表的な語彙に対応する語またはそのなごりが確かに認められます。しかし、衰退していく感じは否めません。*isaはtiti、oɸodi、wodiなどに取って代わられ、*nayoはmeに取って代わられ、omoはɸaɸaに取って代わられ、imoはimoɸitoからimouto(妹)という形で残りましたが、かつてよりだいぶ用法が狭まりました。
日本語に新しい語彙が現れ、ウラル語族との共通語彙が衰退していく構図を見て取った筆者は、その新しい語彙がどこから来たのか考えるようになりました。男と女に関する語彙以外を研究していて、シナ・チベット系言語とベトナム系言語の影響が強いことはわかっていたので、男と女に関する新しい語彙もシナ・チベット系言語かベトナム系言語のものだろうと思っていました。遼河文明の語彙を押しのけることができるとしたら、それは黄河文明の語彙か長江文明の語彙だろうと思っていたのです。
ところがいざ、wotokoはどこから来たのだろう、wotomeはどこから来たのだろう、okinaはどこから来たのだろう、ominaはどこから来たのだろうと調べ始めても、すんなりシナ・チベット系またはベトナム系の語彙に結びつけることができず、ひとまずこれらの問題は棚上げしました。
日本語の中にあるシナ・チベット系の語彙とベトナム系の語彙を相対的に見た場合、日本語とシナ・チベット系言語の接触は広範であり、日本語とベトナム系言語の接触は局所集中的であると感じていたので(日本語はベトナム語が属するオーストロアジア語族全体と接したのではなく、そのごく一部と接したという意味です)、複雑な様相を呈している男と女に関する新しい語彙はシナ・チベット語族のものである可能性が高いと考えていました。
上記の問題を棚上げした筆者は、前々から気になっていたフィンランド語のisäのような語について考察することにしました。かつてウラル語族の人々が祖父、父、その他の年長者に対して広く使っていた語です。現代の感覚からすると不思議なこの語の正体は一体なんなんだろうというのが大きな興味でした。東アジア、特に遼河流域周辺の言語を調べれば、フィンランド語のisäなどと同源の語が見つかるかもしれない、意味や使い方はウラル語族と異なっていても、そこからなにかヒントが得られるかもしれないと考えました。
補説
imo(妹)に対してのse(背、兄)
imo(妹)は男が妻・恋人・姉妹を指す時によく使われ、se(背、兄)は女が夫・恋人・兄弟を指す時によく使われました。対を成していたimo(妹)とse(背、兄)ですが、se(背、兄)の語源はimo(妹)の語源とは全然違うところにあるようです。
タイ語にchaayチャーイという語があります。「男」を意味し、現代では phuu chaay (男の人)プーチャーイや dek chaay (男の子)デクチャーイのように組み込まれて使われるのが普通です(chaayがうしろからphuuとdekを修飾しています)。
ベトナム語にもtraiチャーイという語があります。「男」という意味を持ち、現代では単独で男の集合を意味したり、組み込まれて使われたりします。
タイ語のchaayやベトナム語のtraiを現代の日本語に取り入れるとしたら、tyāiあるいはtyaiとなるところですが、昔の日本語では、そうはいきません。現代の日本人はチャンス、チューリップ、チョコレートなどのように「チャ、チュ、チョ」の類に慣れていますが、昔の日本人は「チャ、チュ、チョ」の類に不慣れであり、「サ、スィ、ス、セ、ソ」の類あるいは「タ、ティ、トゥ、テ、ト」の類で対応するしかありません。おまけに、母音の連続も許されません。タイ系の言語またはベトナム系の言語で「男」を意味していた語を、厳しい制約のある昔の日本語に取り入れる際に、tyaiとできず、tyeともsaiともできず、seになったと見られます。
参考文献
日本語
上代語辞典編修委員会、「時代別国語大辞典 上代編」、三省堂、1967年。
その他の言語
Zaicz G. 2006. Etimológiai szótár: magyar szavak és toldalékok eredete. Tinta Könyvkiadó. (ハンガリー語)