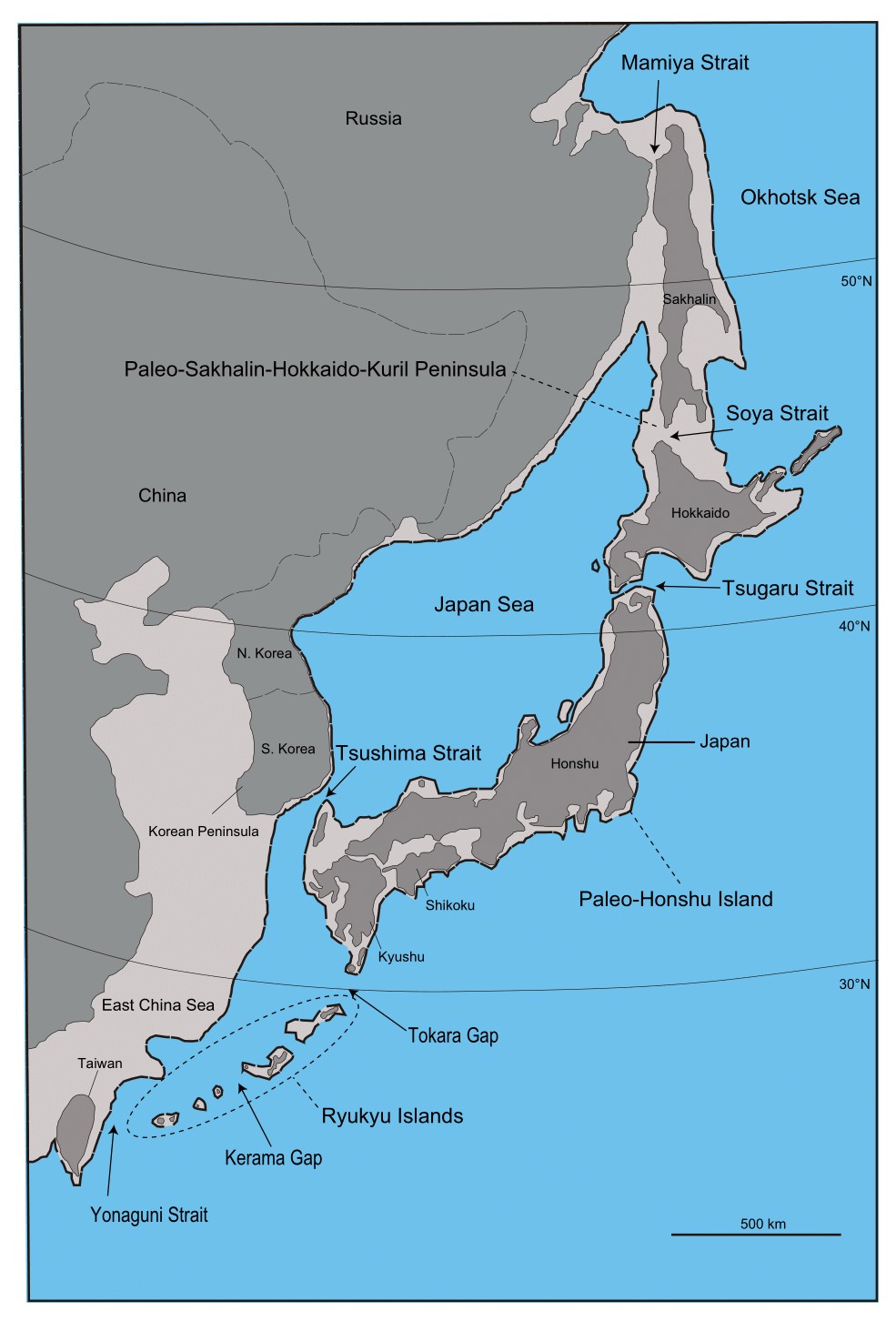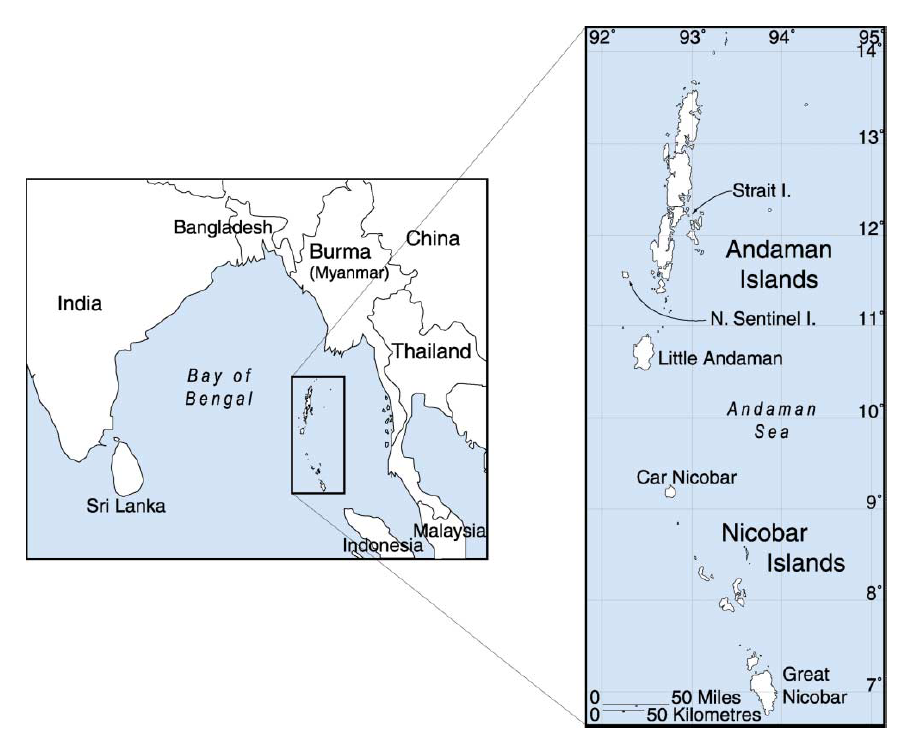すでにお話ししたように、478年に倭の五王の最後の「武」(雄略天皇)が宋に使いを送りましたが、その直後に宋は滅亡してしまいます。これによって、中国への遣使は長く途絶えます。

600年になってからようやく、隋に使いが送られるようになります。中国の歴史書に、再び日本が現れます(以下、隋書の一連の書き下し文は藤堂2010より引用)。
〔隋の〕開皇二十年、倭王の姓は阿毎(あめ)、字は多利思比弧(たりしひこ)、号して阿輩雞弥(あほけみ)というもの、使いを遣わして闕に詣らしむ。
開皇二十年は、西暦600年です。「阿毎(あめ)」、「多利思比弧(たりしひこ)」、「阿輩雞弥(あほけみ)」は、正確性に全く問題がないとは言えませんが、大体の音を表していると考えられます。最後の「阿輩雞弥(あほけみ)」は、「大王(おほきみ)」を指しているのでしょう。
阿毎多利思比弧(あめたりしひこ)はどう理解したらよいか▶
中国側は、阿毎(あめ)は姓、多利思比弧(たりしひこ)は字と解釈したわけですが、これは極めて不確かです。
例えば、卑弥呼(ひみこ)と卑弥弓呼(ひみくこ)、なぜこんなに名前が似ているのか、両者の関係とはの記事でお話ししたように、ɸimikoは、人名ではなく、地位に付けられた名であったと考えられます。ところが、中国人と日本人の間で以下のような会話が交わされます。
中国人「一番偉い人はなんて言うの」
日本人「ɸimikoと言います」
中国人「ああ、そう、ɸimikoね」
このようにして、ɸimikoが人名として扱われてしまいます。
問題の阿毎多利思比弧(あめたりしひこ)はどうでしょうか。阿毎多利思比弧(あめたりしひこ)が大体の音を表していることは間違いなく、これと古代日本語の語彙を照らし合わせると、筆者は以下のようになるのではないかと考えています。
少し後の時代になりますが、奈良時代の日本語には、oru(下る)、kudaru(下る)、sagaru(下がる)という語がありました。これらのほかに、taru(垂る)という語もありました。taru(垂る)は四段活用です。

奈良時代の日本語のtaru(垂る)は、現代の日本語のtareru(垂れる)と同じような意味を持っていましたが、この語はもともと、oru(下る)、kudaru(下る)、sagaru(下がる)と同様に、下への動きを意味していたと思われます。
上記の記事で説明したように、ɸikoは、統治者・支配者を意味する語が、目上の男に対する敬称になったものですから、阿毎多利思比弧(あめたりしひこ)は、ame+tarisi+ɸikoという構造で(もっと細かく言うと、tariは動詞taruの連用形、siは過去の助動詞kiの連体形)、「天から降りて来られた統治者・支配者」あるいは「天から降りて来られたお方」のような意味だったと考えられます。天から降りて来ることをamakudaru(天下る)と言うのと同じ理屈です。
阿毎多利思比弧(あめたりしひこ)は、このように日本語の中に位置づけるのが自然でしょう。人名というより、定型句です。
その後に、以下の記述があります。
王の妻は雞弥(けみ)と号す。後宮には女六七百人有り。太子を名づけて利歌弥多弗利と為す。
読み進むと、よく知られている以下の場面が出てきます。
〔隋の〕大業三年、其の王多利思比弧、使いを遣わして朝貢せしむ。使者曰く、「聞く、海西の菩薩天子、重ねて仏法を興すと。故に遣わして朝拝せしめ、兼ねて沙門数十人来たりて仏法を学ばしむ」と。其の国書に曰く、「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙無きや云云」と。帝、之を覧て悦ばず、鴻臚卿に謂いて曰く、「蛮夷の書、無礼なる者有り、復た以て聞する勿かれ」と。
大業三年は、西暦607年です。倭王阿毎多利思比弧の文書を受け取って、隋の皇帝が怒ってしまった場面です。
倭の五王の最後の「武」(雄略天皇)が宋の皇帝に送った文書を思い出してください(藤堂2010)。
もう一度読む▶
順帝の昇明二年(四七八年)に、倭王武は使者を遣わして上表文をたてまつって言った。
「わが国は遠く辺地にあって、中国の藩屏となっている。昔からわが祖先は自らよろいかぶとを身に着け、山野をこえ川を渡って歩きまわり、落ち着くひまもなかった。東方では毛人の五十五ヵ国を征服し、西方では衆夷の六十六ヵ国を服属させ、海を渡っては北の九十五ヵ国を平定した。皇帝の徳はゆきわたり、領土は遠くひろがった。代々中国をあがめて入朝するのに、毎年時節をはずしたことがない。わたくし武は、愚か者ではあるが、ありがたくも先祖の業をつぎ、自分の統治下にある人々を率いはげまして中国の天子をあがめ従おうとし、道は百済を経由しようとて船の準備も行った。
ところが高句麗は無体にも、百済を併呑しようと考え、国境の人民をかすめとらえ、殺害して、やめようとしない。中国へ入朝する途は高句麗のために滞ってままならず、中国に忠誠をつくす美風を失わされた。船を進めようとしても、時には通じ、時には通じなかった。わたくし武の亡父済は、かたき高句麗が中国へ往来の路を妨害していることを憤り、弓矢を持つ兵士百万も正義の声をあげていたち、大挙して高句麗と戦おうとしたが、その時思いもよらず、父済と兄興を喪い、今一息で成るはずの功業も、最後の一押しがならなかっ た。父と兄の喪中は、軍隊を動かさず、そのため事を起こさず、兵を休めていたので未だ高句麗に勝っていない。
しかし、今は喪があけたので、武器をととのえ、兵士を訓練して父と兄の志を果たそうと思う。義士も勇士も、文官も武官も力を出しつくし、白刃が眼前で交叉しても、それを恐れたりはしない。もし中国の皇帝の徳をもって我らをかばい支えられるなら、この強敵高句麗を打ち破り、地方の乱れをしずめて、かつての功業に見劣りすることはないだろう。かってながら自分に、開府儀同三司を帯方郡を介して任命され、部下の諸将にもみなそれぞれ官爵を郡を介して授けていただき、よって私が中国に忠節をはげんでいる」と。
そこで順帝は詔をくだして武を、使持節・都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六国諸軍事・安東大将軍・倭王に任命した。
「武」(雄略天皇)は、中国の皇帝に従属する態度・姿勢をはっきりと見せています。自分の地位も、中国の皇帝によって認定されるものと考えています。この態度・姿勢は、卑弥呼の時代から倭の五王の時代になっても一貫していました。
しかし、倭王阿毎多利思比弧の「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す」という言葉は、それとはかなり異なっています。もちろん、この倭王は中国の皇帝を侮辱あるいは挑発しようと思ったわけではないでしょう。その前の部分で学ぼうとする意思を示しているのですから、そんなことをするはずがありません。しかし、478年の倭王と600年の倭王で、態度・姿勢が大きく変わったのも事実なのです。
これは、571年に死亡した欽明天皇の五条野丸山古墳(ごじょうのまるやまこふん)が最後の巨大前方後円墳になったこととよく合います。
「倭の五王」をめぐる論争の行方、いわゆる「応神天皇陵」と「仁徳天皇陵」についての記事でお話ししたように、考古学など全く存在しない時代の古事記と日本書紀の制作者は、古代日本の最高位の者の墓が三輪山の麓から佐紀に移り、佐紀から河内・和泉に移ったことを正確に知っていました。古事記と日本書紀が書かれる前に、古代日本の最高位の者の墓が三輪山の麓から佐紀に移り、佐紀から河内・和泉に移る過程を詳しく記した書物があったわけです。冒頭の図の時代の各倭王も、日本という国ができた時から歴代の倭王の墓が巨大な前方後円墳として作られてきたことを知っています。応神天皇のところと継体天皇のところは大きな節目ですが、それでも倭王の墓は巨大な前方後円墳として作られ続けました。
このように日本という国の始まりから続いてきた長い伝統を断ち切るというのは、並大抵のことではありません。前方後円墳は、なんとなく終わるものではなく、「これからは別の国になるのだ」ぐらいのことを考える大胆不敵な倭王が現れないと、終わりそうにないものなのです。478年の倭王と600年の倭王の態度・姿勢の違いは、このことをよく示しています。
607年に倭王阿毎多利思比弧の文書が隋の煬帝を怒らせてしまうというハプニングがありましたが、翌608年に今度は煬帝が裴世清らを日本に送ります。この裴世清らが、貴重な目撃者になるのです(以下、隋書の一連の書き下し文と現代語訳は藤堂2010より引用)。
明年、上、文林郎裴清を遣わして倭国に使いせしむ。
裴世清らの一行は、長旅を経て、都に到着し、倭王と会います。
倭王、小徳阿輩台を遣わし、数百人を従え、儀仗を設け、鼓角を鳴らして来り迎えしむ。後十日、又大礼哥多毗を遣わし、二百余騎を従え郊労せしむ、既にして彼の都に至るに、其の王、清と相見て、大いに悦びて、曰く、
「我聞く、海西に大隋有り、礼儀の国なり。故に遣わして朝貢せしむ。我は夷人にして、僻りて海隅に在り、礼儀を聞かず。是を以って境内に稽留して、即ち相見えず。今故に道を清め館を飾り、以って大使を待つ。冀わくは大国惟新の化を聞かん(海を渡った西方に大隋国という礼儀の整った国があると、私は聞いていた。そこで使者を遣わして貢ぎ物を持って入朝させた。私は野蛮人であり、大海の一隅に住んでいて、礼儀を知らない。そのために今まで国内に留まっていて、すぐには会えなかった。今、特に道を清め、館を飾って裴大使を待っていた。どうか大隋国の新たな教化の方法を聞かせてほしい)」と。
清、答えて曰く、
「皇帝の徳は二儀に並び、沢は四海に流る。王、化を慕うを以って、故に行人を遣わし、此に来り、宣べ諭さしむ(皇帝の徳の明らかなことは日月と並び、その恩沢は四海に流れ及んでいる。倭国王は隋の皇帝の徳を慕って教化に従おうとしているので、皇帝は使者を遣わしてこの国に来させ、ここに宣べ諭させるのである)」と。
ここに出てくる倭王は、一体だれなのでしょうか。
衝撃的な著作「天孫降臨の夢 藤原不比等のプロジェクト」を出した大山誠一氏も、当然この点に注目しています。大山氏は、以下のように述べています(大山2009)。
これまで、繰り返し、『日本書紀』の記述が虚構に満ちていると述べてきた。しかし、実は、事実を記した部分もある。推古朝の場合、冠位十二階とか小野妹子の遣隋使など、中国の史書である『隋書』によって事実と確認できるものもある。また、飛鳥寺はもちろん、小墾田宮や飛鳥岡本宮なども、存在自体は考古学により確認されている。もちろん、斑鳩宮と斑鳩寺(法隆寺)の建立も事実である。真実の断片は、決して少なくはないのである。
しかし、そうした中で、大きな謎がある。六〇八年に隋の皇帝煬帝が、裴世清を国使として遣わしたことはよく知られている。そこで裴世清が会った倭王は男性であったと書かれている。倭王は、裴世清のために饗宴を催してもいる。倭王には妻がおり、後宮もあったという。大勢の使者たちの見聞にもとづいた記事である。嘘ではあるまい。では、冠位十二階を制定し、遣隋使を派遣した倭王は誰だったのか。当時の倭王を『日本書紀』は推古としている。日本史の教科書にもそう書かれている。しかし、『隋書』の記述を信用すると、少なくとも女性の推古ではなさそうである。何しろ、妻と後宮があるのだから。これまでの研究者は、この問題を避けてきた。しかし、もはや、避けるわけにはゆかないだろう。
大山氏が指摘するように、まず重要なのは、倭王には妻がいて、後宮があったということです。「妻」も、「後宮」も、隋書原文にある表現です。後宮とは、皇帝の妻と子どもが住む、一般に男子禁制の場所です。中国人のいう「後宮」とは、このような場所です(画像は中華歴史ドラマ列伝様のウェブサイトより引用)。

※隋書原文では「妻」と「後宮」の後に「太子」という表現も見られますが、太子とは、皇帝の長男(皇位を継ぐ予定の者)です。
倭王は男なのです。隋の煬帝が遣わした裴世清は、倭王と会い、倭王と言葉を交わしています。推古天皇ではなく聖徳太子を倭王と間違えたという説明は成り立ちません。天皇の代わりに政務を執り行うにすぎない摂政のために後宮があるわけはないからです。
日本書紀は、593~628年は推古天皇の時代であると言っています。日本書紀の推古天皇の巻はどう書かれているのでしょうか。推古天皇の巻の最初のほうで「厩戸豊聡耳皇子を立てて、皇太子とされ、国政をすべて任せられた」と述べられているように、推古天皇という人物は、もともと存在感が希薄でした。しかし、隋の皇帝が使いを送ったのですから、さすがにこれを推古天皇の巻から省くことはできません。推古天皇の巻の記述は大変怪しげです(以下、日本書紀の一連の現代語訳は宇治谷1988より引用)。
※日本書紀は、隋のことを「大唐」または「唐」と記します。日本書紀が書かれたのが完全に唐の時代であったことが大きいと思われます。私たちは、現代について語る時だけでなく、古代について語る時にも「中国」と言いますが、それに似た感覚でしょう。
秋八月三日、唐の客は都へはいった。この日飾馬七十五匹を遣わして、海石榴市の路上に迎えた。額田部連比羅夫が挨拶の言葉をのべた。
十二日、客を朝廷に召して使いの旨をのべさせられた。阿倍鳥臣・物部依網連抱の二人を、客の案内役とした。唐の国の進物を庭上に置いた。使者裴世清は自ら書を持ち、二度再拝して使いの旨を言上した。その書には、「皇帝から倭皇にご挨拶を送る。使人の長吏大礼蘇因高らが訪れて、よく意を伝えてくれた。自分は天命を受けて天下に臨んでいる。徳化を弘めて万物に及ぼそうと思っている。人々を恵み育もうとする気持には土地の遠近はかかわりない。天皇は海のかなたにあって国民をいつくしみ、国内平和で人々も融和し、深い至誠の心があって、遠く朝貢されることを知った。ねんごろな誠心を自分は喜びとする。時節は漸く暖かで私は無事である。鴻臚寺の掌客裴世清を遣わして送使の意をのべ、併せて別にあるような送り物をお届けする」とあった。そのときに阿倍鳥臣が進み出て、その書を受けとり進むと、大伴囓連が迎え受けて、帝の前の机上に置いた。儀事が終って退出した。このときには皇子・諸王・諸臣はみな冠に金の飾りをつけた。また衣服にはみな錦・紫・繡・織および三色織りのうすものをもちいた。
十六日、客たちを朝廷で饗応された。
※宇治谷1988の現代語訳では「帝の前の机上に置いた」と訳されていますが、日本書紀原文の表現は、「帝」ではなく、「大門」です。「宮門」を通ると、「朝庭」が広がっており、そこを突っ切って「大門」を通ると、天皇の居所である「大殿」があるという具合です。
すごいハイライトシーンです。「あれっ、倭王のお出ましは?」と唖然としてしまいます。これは、隋の使いを迎える場面ですが、少し後に、新羅・任那の使いを迎える場面も記されています。
冬十月八日、新羅・任那の使人が都に到着した。この日、額田部連比羅夫に命ぜられて、新羅の客を迎える荘馬の長とし、膳臣大伴を任那の客を迎える荘馬の長とした。大和の阿刀の河辺の館に入らせた。
九日、客人たちは帝に拝礼した。このとき秦造河勝・土部連菟に、新羅の導者を命ぜられた。間人連塩蓋・阿閉臣大籠に任那の導者を命ぜられた。共に南門から入って御所の庭に立った。大伴咋連・蘇我豊浦蝦夷臣・坂本糠手臣・阿倍鳥子臣らは、席から立って中庭に伏した。両国の客人はそれぞれ拝礼して使いの旨を奏上した。四人の大夫は前に進んで大臣に申し上げ、大臣は席を立ち、政庁の前に立って聴いた。終って客人らにそれぞれに応じた賜物があった。
十七日、使者たちを朝廷でもてなされた。河内漢直贄を、新羅の客の相手役とし、錦織首久僧を任那の客の相手役とした。
※宇治谷1988の現代語訳では「客人たちは帝に拝礼した」と訳されていますが、日本書紀原文の表現は、「帝」ではなく、「朝庭」です。「宮門」を通ると、「朝庭」が広がっており、そこを突っ切って「大門」を通ると、天皇の居所である「大殿」があるという具合です。「(政)庁」は、「朝庭」の脇にあります。
新羅・任那の使いが来た時も、隋の使いが来た時と同じ流れですが、「大臣」が現れて終わっています。
大山氏は、これらの二つの場面にも厳しい目を向けます(大山2009)。
そこで、今度は、裴世清に関する『日本書紀』の記事を見ておこう。歓迎行事の中で、倭王がどのように記されているかを確認する必要があるからである。
推古十六年(六〇八)八月壬子条に、その様子が記されている。まず、裴世清が朝庭に召され、日本側の役人が使者の趣を奏上する。阿倍鳥臣と物部依網連抱とが導者となって国信物を庭中に置く。次に、裴世清が自ら国書を読み上げる。それが終わると、阿倍臣がその国書を受け取り、さらにその国書を大伴囓連が受け取って、大門の前の机の上に置き、その旨を奏上する、というものである。ここで、終わっている。要するに、国書をたらい回しして大門の前の机の上に置いたまま終わっているのである。ここで、天皇制という迷信にどっぷり浸かっている人は、天皇を神と考え、使者の前には姿を現さなかったと解釈する。天皇はシャーマンのような神秘的な存在で、邪馬台国の卑弥呼も人々の前には姿を現さなかったではないかというわけである。
しかし、そうではない。ここは、『隋書』によるべきである。倭王は、間違いなく、裴世清と言葉を交わしている。卑弥呼の例をもち出すなど時代錯誤もはなはだしい。倭王が登場しないのは、『日本書紀』が都合が悪かったので書かなかったためと考えるべきである。
しかし、実は、『日本書紀』には、このときの倭王が誰かを推測できる記事がある。新羅と任那の使者に対する歓迎行事の記事である。
推古十八年(六一〇)十月丁酉条に、その記事がある。
まず、隋の使者の場合と同様に、秦造河勝と土部連菟が新羅の導者、間人連塩蓋と阿閉臣大籠が任那の導者となり、両国の使者を案内して南門より朝庭に入る。そのとき、大伴咋連・蘇我豊浦蝦夷臣・坂本糠手臣・阿倍鳥子臣の四人の大夫が席を起って、庭に伏す。両国の使者が、再拝して使の趣旨を言上する。そして、ここからである。先の四人の大夫が起って進んで大臣に奏上し、大臣は、席から起って、庁の前でこれを聞く。その後、使者たちに禄を与えて終わるのであるが、実質上、大臣の登場が儀式の最後と言ってよい。使者たちは、導者と四人の大夫に導かれて、最後に大臣と接見したのである。この大臣こそ、この儀式の主役だったと言ってよい。もちろん、ここで言う大臣とは蘇我馬子のことである。
これが日本の歴史書の推古天皇の巻であり、隋の皇帝が使いを送ってきたというビッグイベントの時の記述なのですから、やはり異常と言うしかないでしょう。隋書が倭王が裴世清と会うシーンを実直に記しているだけに、日本書紀の異常さが際立ちます。
倭王阿毎多利思比弧の文書が隋の煬帝を怒らせてしまうハプニングはありました。倭王阿毎多利思比弧は、「怒らせてしまったのなら、申し訳ない」という趣旨のことは言ったでしょう。中国との接触を再開した後の日本の改革を見ると、倭王阿毎多利思比弧は、中国が日本よりはるかに進んでいることを十分に認識しており、張り合うような態度には見えません。ただ、自分の地位が中国の皇帝によって認定されるものとは考えておらず、この点は昔の倭王と異なっています。
卑弥呼と台与のこともそうでした。古事記と日本書紀がとぼけようとしても、魏志(魏書)が本当のことを暴露していました。継体天皇の勾大兄皇子と檜隈高田皇子のこともそうでした。古事記と日本書紀がとぼけようとしても、百済本記が本当のことを暴露していました。推古天皇と聖徳太子と蘇我馬子のこともそうなのです。古事記と日本書紀がとぼけようとしても、隋書が本当のことを暴露しているのです。
めまいがしそうですね。日本の飛鳥時代が崩壊?いや、そんなことはありません。長く続いた古墳時代から飛鳥時代への移行は、まぎれもなく日本史上の大きな転機です。ただ、新たな方向へ舵を切ったのが、推古天皇の代わりをしていたという聖徳太子ではなく、蘇我馬子だった可能性が出てきたということです。
古事記と日本書紀は、膨大な嘘を積み重ねています。しかし、無秩序に嘘を積み重ねているわけではありません。ある目的があるのです。その目的とは、「万世一系」というフィクションを作り上げ、それを真実として信じ込ませることです。古事記と日本書紀は、そのための執念のかたまりと言っても過言ではありません。だれがそのような狂気のフィクションを作り上げようとし、実際に作り上げたのか、それを完璧に明らかにしたのが、ほかならぬ大山誠一氏の「天孫降臨の夢 藤原不比等のプロジェクト」です。
前回の記事で敏達天皇の実在性が危うくなってきましたが、推古天皇の実在性も危うくなってきました。ある男女が実在したことは認めているのです。その男女が天皇だったのか問題にしているのです。
蘇我馬子は、敏達天皇→用明天皇→崇峻天皇→推古天皇という四人の天皇の時代に大臣だったことになっています。敏達天皇と推古天皇だけでなく、用明天皇と崇峻天皇も調べないといけないでしょう。
参考文献
宇治谷孟、「日本書紀(上)」、講談社、1988年。
大山誠一、「天孫降臨の夢 藤原不比等のプロジェクト」、NHK出版、2009年。
藤堂明保ほか、「倭国伝 中国正史に描かれた日本 全訳注」、講談社、2010年。